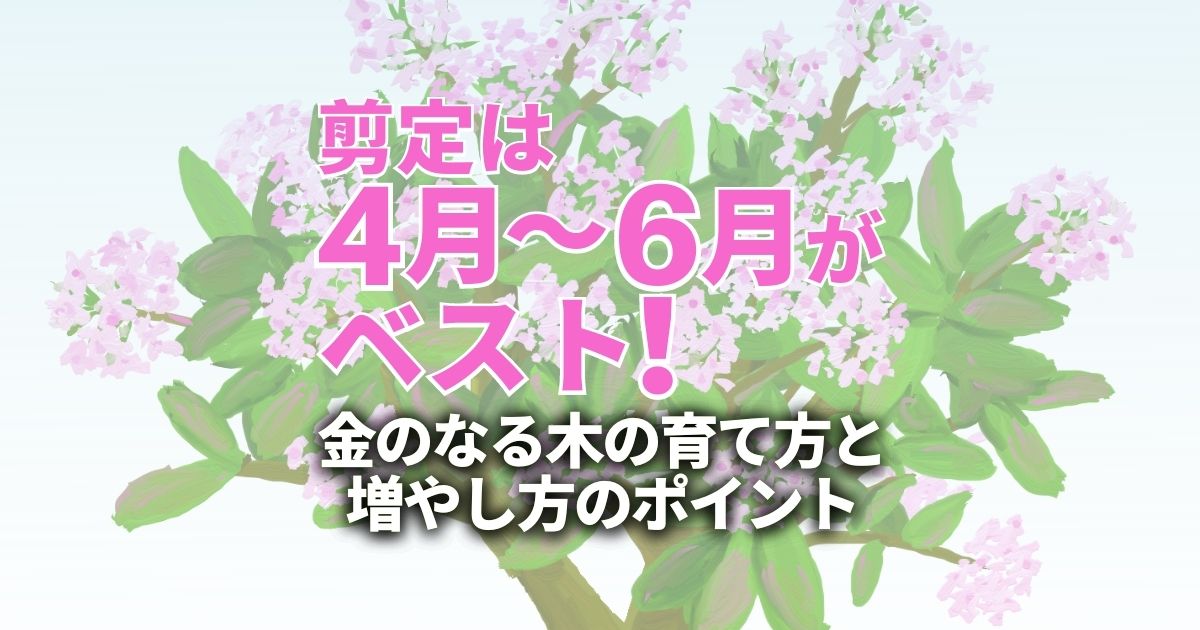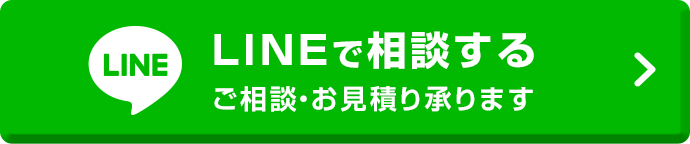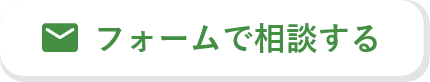丈夫で育てやすい金のなる木は初めて観葉植物を育てるという人が選ぶことも多いですが、その分トラブルを抱えることもあるようです。
また、上級者であれば「挿し木で増やしたい」という人もいるでしょう。
この記事では、金のなる木の剪定、挿し木の時期と方法、元気がなくなってしまったときの原因と対処法を解説します。
観葉植物のトラブルはさまざまな原因によって起こるので、自分ではどうすればよいのかわからないこともありますよね。
- 葉や枝が弱っている
- 病気や害虫が発生してしまった
- 自分でうまく剪定できるか不安
観葉植物にも詳しい樹木のプロであれば、トラブルの原因を究明して根切りや植え替え、害虫の駆除など適切な対処をしてくれます。
剪定や消毒による病害虫の予防をお任せすることもできるので、育て方に悩んだときにはプロに相談してみるのがおすすめです。
金のなる木の剪定方法と時期
鉢植えで観葉植物として育てられることが多い金のなる木ですが、地植えであれば3mほどの高さまで成長することもある木です。
鉢植えでも植え替えを繰り返しているうちに、置いておきづらい大きさになってしまうこともあります。
大きくて扱いづらくなった金のなる木は、剪定で枝を切って小さくまとめましょう。生命力の強い金のなる木は、枝を短く切っても新たな芽を伸ばして成長し続けることができます。
また、枝を土に挿して株を増やす挿し木をするときにも、剪定は必要な作業です。
まずは基本的なお手入れの1つである剪定の時期や方法について理解していきましょう。
金のなる木の剪定時期

金のなる木の剪定時期は、4月~10月頃であれば問題はありません。
特におすすめな時期は4月~6月頃です。
金のなる木は暑さには強いですが寒さに弱いです。
気温の低い時期に剪定をすると、木が剪定のダメージに耐えることができず枯れてしまうおそれがあります。
そのため、冬場の剪定は厳禁です。
金のなる木の開花時期は11月~2月頃ですが、8月頃から枝に花の芽を作り始めます。
そのあとに枝を切ると、花の芽を一緒に切り落としてしまい花が咲かなくなるおそれがあるのです。
夏の成長期前である4月~6月頃は体力も早く回復します。
鉢植えの場合は植え替えの適期も同じ時期なので、まとめて済ませてしまうのもおすすめです。
金のなる木の剪定方法
生命力の強い金のなる木の剪定は、それほど難しくはありません。
どの位置で枝を切っても、力強く新しい芽を出してくれます。
ただし、金のなる木は成長がゆっくりなので、早く樹形を整えたい場合は枝の分岐点の少し上で切るようにしましょう。
若くて細い枝を残して太い枝を切ると、全体を小さくまとめることができます。
剪定で切り落とした枝や葉は、挿し木に利用することができます。
詳しくは後述の「剪定した葉や枝で簡単に増やせる!」をご覧ください。
金のなる木が伸びすぎる原因
基本的には頻繁な剪定は必要ない金のなる木ですが、枝だけがひょろひょろと伸びて不格好な印象になってしまうと剪定で整えたくなりますね。
では、どのようなときに枝が伸びすぎてしまうのでしょうか。
その原因を知っておけば、樹形が乱れるのを予防できます。
日照不足
金のなる木は基本的に日光が大好きです。
日光が当たらない場所に置かれていると、日光を求めて枝だけが伸びすぎてしまいます。
室内なら窓辺など、十分に日光が当たる場所に置いてあげましょう。
ただ、真夏の強すぎる日差しは少し苦手です。
暑い時期にはある程度の涼しさもある半日陰に置くことをおすすめします。
水分のあげすぎ
次に考えられる原因は水分のあげ過ぎです。
水分を必要以上に与えることで、葉が張った状態になり、枝はひょろひょろと伸びてしまいます。
枝がふにゃふにゃになって垂れ下がったり、折れたりすることもあります。
また、水をあげすぎて土が湿った状態が続いていると、根腐れを起こして枯れてしまう原因にもなるのです。
金のなる木は乾燥を好む多肉植物であるため、水はあまりあげる必要がないのです。夏場は土が乾いてから1~2日後に水をあげましょう。
土が乾燥しにくい冬場は月に1回程度で十分です。
肥料のあげすぎ
多肉植物はもともと栄養の少ない環境で育つ植物なので、基本的に肥料は必要ありません。
肥料で栄養のあげすぎることで、本来の成長スピード以上に成長してしまうのです。
肥料をあげるのであれば、植え替えをするときに緩効性の固形肥料などを土に混ぜ込むのみで十分です。
金のなる木の管理が難しいときはプロに相談!
単に枝を切るだけなら難しくはありませんが、枝の伸び方や成長速度を考えながら樹形を整えるのは初心者にとっては難しく感じることもあります。
特に大きくなりすぎてしまったときや樹形が乱れてしまったときは、どこをどの程度切ればよいのか迷ってしまうことも多いものです。
そんなときに頼りになるのがプロの存在です。
プロは金のなる木の生育状況を観察し、適切な剪定ができます。
プロに見ててもらえば、日照不足や水のあげすぎなどの健康状態も確認して対処することができるのです。
金のなる木など観葉植物の剪定料金は3,000~10,000円ほどとなっています。
料金は木の大きさによって変わり、出張料などが重なると高くなってしまうこともあります。
まずは見積りを取って料金を確認しましょう。
剪定した葉や枝で簡単に増やせる!

金のなる木は、剪定した葉や枝を使って簡単に増やすことができます。
枝や葉を使用した木の増やし方をご紹介します。
挿し木で増やす方法
まずは剪定したあとの枝を使用した方法です。
時期は5~8月頃をおすすめします。
- 葉がついたままの5~20cmほどの枝を用意する
- 枝の切り口が濡れていないようにしっかりと日陰で乾燥させる
- 下の方についている葉を切り落とす
- 切り落とした枝が濡れていないことを確認したのちに土に挿す
- 水を与えずに1ヵ月ほど様子をみて、根が出たら鉢などに植え替える
この流れで大切なポイントとなるのが、枝をしっかりと乾燥せることです。
乾燥していないままだと切り口から雑菌が入りこんで発育しないおそれもあるため、しっかりと乾かしましょう。
葉挿しで増やす方法
続いて、葉を利用した葉挿しという方法の解説をします。
- 特に大きく育っている葉を枝から摘み取る
- 2日ほど日陰に置いて、葉を乾燥させる
- 水はけのよい川砂などに葉の切り口を挿す
- 水を与えず1ヵ月ほど様子をみて、芽が確認できたら鉢などに植え替える
金のなる木でも水栽培が可能
金のなる木は水栽培で育てることも可能です。
水栽培であれば水やりの必要がなくなるので楽ですよね。
そんな金のなる木の水栽培に必要なものと手順をご紹介していきます。
- 金のなる木
- 金のなる木が落ちない口の大きさの瓶
- 水栽培専用の液体肥料
- 園芸用ハサミ
- 金のなる木を鉢から取り出し、土を落とすために水洗いをして、しっかりと乾かす
- 消毒した園芸用ハサミで根を少し残すような状態で切る
- 用意した瓶に水と水栽培用肥料を入れて、金のなる木を根の先端だけが水につかるように挿す
- 週に1回程度水替えをする
金のなる木を水栽培するポイントは、水栽培に適応させるために根を一度切ってしまうという点です。
土栽培の場合は、土の中の水を求めて根は下へ下へと長く伸びますが、水栽培では水を探す必要がないので、根の伸び方が違うのです。
少し根を残した状態で水につけることで、水栽培に適応した根が伸びてきます。
金のなる木を増やすなら、剪定をして繁殖させよう!
金のなる木を増やしたいなら、枝の剪定と同時におこなうのがおすすめです。
剪定には枝葉の量を調整して日当たりや風通しを改善する効果もあります。
もし、剪定の依頼を検討しているのなら、ぜひ弊社にご相談ください。
お近くの剪定業者のなかから、金のなる木の剪定を得意としている業者をご紹介させていただきます。
「まずは相談だけ」というお問い合わせももちろん承っております。
金のなる木の葉がしわしわになる原因
気を付けて育てているはずでも、金のなる木の葉がしわしわになったり、落ちてしまったりといったトラブルが起きることがあります。
原因と対処法をご紹介します。

金のなる木の葉がしわしわになってしまう原因は、水不足であることが多いです。
葉に蓄えている水分が少なくなると、葉がしぼんでしわしわになります。
逆に水のあげすぎで根腐れを起こし、水分を吸い上げられなくなって逆に水不足になることもあります。
根が元気であれば、適切に水やりをすれば回復します。
水やりの頻度を極端に増やすと根腐れするおそれがあるので、水を与えたら土が乾くまで水やりはしないようにしましょう。
すでに根が腐ってしまっている場合は「根切り」をします。
傷んだ根を切り落とすことで回復する可能性があるのです。
一度鉢から出して根の黒くなった部分を切り落とし、切り口が乾燥してから植え直しましょう。
金のなる木の葉が落ちる原因
金のなる木の葉が落ちるおもな原因は日光不足です。
毎日適度に日光を浴びせるようにしましょう。
また、冬などの冷える時期には太陽の出ていない時間帯には暖かい場所に移動させてあげることで、金のなる木の葉が落ちるのを防ぐことができます。
また、根腐れによっても葉が落ちることがあります。
水の与えすぎには注意しましょう。
金のなる木を育てる際のポイント
金のなる木を枯らさずにために大切な4つのポイントをご紹介します。
日当たりがよく暖かい場所に置く
金のなる木は日光をとても好みます。
そのため、日中は日当たりのよい場所においてあげましょう。
また、霜をとても苦手としているため、真冬は室内に移動することをおすすめします。
夏と冬で水やりの頻度を調整する
金のなる木の水やりは湿気に弱く、乾燥に強いという性質を意識しながらおこないましょう。
水のあげ過ぎは厳禁です。
根腐れをおこし、枯れてしまうおそれがあるため注意しましょう。
夏場は土が乾いて数日置いてから、たっぷり水を与えます。
冬場はさらに水をあげる頻度を落として構いません。
月に1回ほどで十分です。
冬の間は日光を浴びせることも意識しましょう。
肥料は控えめにする
少ない栄養でもしっかりと成長する金のなる木は、肥料をあげなくても基本的には育ちます。
もしあげるなら、水はけのよい土で4~10月の発育期に液体の肥料や、置き肥料をあげましょう。
ただし、あまり肥料を好む植物ではないということを念頭に置き、あげ過ぎには注意しましょう。
植え替えはほとんど必要ない
植え替えはほとんど必要がありません。
おこなうとしても2~3年に1回ほどのペースで構いません。
今よりも少し大きいサイズの鉢に4~6月頃に植え替えてあげましょう。
金のなる木で注意が必要な病害虫
金のなる木に発生しやすい害虫が、カイガラムシです。
カイガラムシは5月~8月頃に発生しやすい、体長2mm程度の昆虫です。
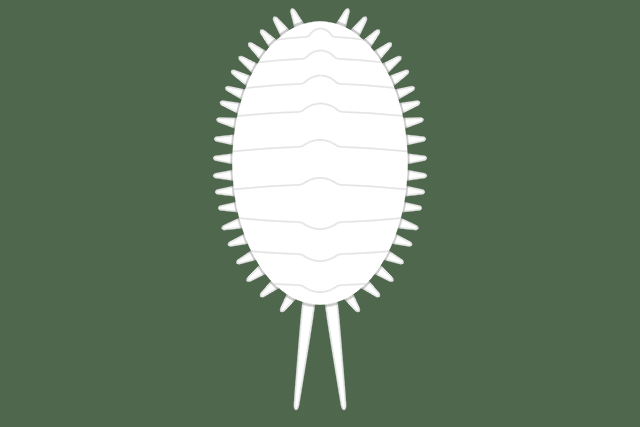
寄生すると集団で樹液を吸い取って植物を弱らせるだけでなく、菌が繁殖することですす病やこうやく病などさまざまな病気の原因になります。
金のなる木にカイガラムシが発生してしまった場合は、歯ブラシなどを使って引きはがしたり、殺虫剤を使ったりして早めに駆除しましょう。
また、うどんこ病も金のなる木で気を付けたい病気です。
うどんこ病とは、植物に糸状菌と呼ばれるカビの菌が住み着いて葉が白く変色してしまう病気です。
うどんこ病にかかった部分は光合成ができず枯れてしまいます。
金のなる木がすす病やこうやく病、うどん粉病にかかってしまった場合は、症状が出ている箇所を切り落としましょう。
さらに残っている菌が繁殖してしまうのを防ぐために、専用の治療薬剤を散布しておくのがおすすめです。
剪定・消毒に悩んだらプロに頼る
植物に発生する害虫や病気は原因の特定が難しく、どのような対処をすれば回復できるのか自分では判断できないこともありますよね。
金のなる木にトラブルが発生したときには、樹木のプロに相談してみましょう。
樹木の特性について知識と経験の豊富なプロは、金のなる木の状態を見て病害虫が発生しているのか、水や肥料のやりすぎなのかといった原因を的確に究明してくれます。
害虫や病気に対する適切な薬剤の散布、剪定や根切り、植え替えなどの対処であらゆるトラブルを解決してくれます。
また、剪定や植え替えなどの定期的な手入れをプロにしてもらえば、その際に樹木の状態をチェックして病気などの早期発見にもつながります。
観葉植物や庭木の育て方に関する相談に乗ってもらえることもありますので、一度話だけでも聞いてみると今後の参考になりますよ。
金のなる木のお悩みは剪定110番にご相談ください!
金のなる木の剪定やお手入れを業者に頼みたいと思っても、「どこに頼めばいいのかわからない」ということもあるでしょう。
観葉植物にも対応している業者を探したり、見積りを取って料金を比較したりするのは正直面倒ですね。
そんなときには、剪定110番がお役に立ちます。
剪定110番では全国のさまざまな剪定業者と提携をしており、
ご相談内容に応じた最適なプロをご紹介できます。
金のなる木などの観葉植物を得意としている業者も在籍しています。
見積り、見積り後のキャンセルは無料※となっており、ご相談だけなら費用はかかりませんのでご安心ください。
※対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。
24時間365日受付対応の窓口でご相談を受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。